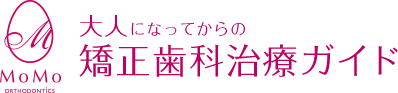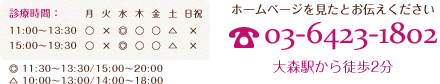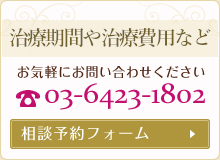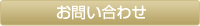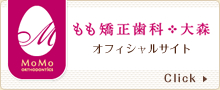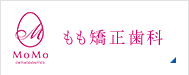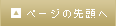スタッフブログ
2015年10月21日 水曜日
上顎前突を子供のうちに治すメリット
今までに見た目の改善に意識が向きやすい上顎前突(出っ歯)に関して、指しゃぶりなどの日々の習慣が原因のもの、骨格性のものと種類があることをご説明しました。また上顎前突からくるトラブル、虫歯や歯周病などにつながるリスクに関してご紹介しました。
今回は子供のうちに上顎前突を治すメリットをお伝えしたいと思います。
① 指しゃぶりなどの生活習慣から起こる上顎前突
歯は弱い力でも動くということは以前お伝えした通りです。指しゃぶりなどの力が継続的に歯に加わることでも上顎前突になる場合があります。この場合の上顎前突治療は歯並びを治すだけでなく、そういった癖を同時に治していく必要が出てきます。ブラケット(矯正装置)を外した後の保定装置期間において、後戻りを起こさないためにも、もともと上顎前歯が前に出る原因となっていた癖を若いうちに治すことが長期での安定につながります。大人になってからでは癖を治せないということはありませんが、子供のうちの方が習慣を変えやすかったりします。
②骨格性上顎前突
骨格性の上顎前突とは、簡単に言うと上下の顎の大きさの違いによるもの、噛み合わせのズレによるものなどを指します。歯並びだけでなく、顎の骨に関係しているため、子供のうちに治すメリットとしては、顎の成長をある程度コントロールしながら矯正治療を行える点です。
どちらの原因の場合も、子供から治療を開始することで永久歯列で抜歯することなく治療を完了できる可能性が大きくなります。
後戻りのリスクを下げること、骨の成長を考えての歯列矯正を行うことに関しては、実は下顎前突(受け口・しゃくれ)や叢生(デコボコ)においても、同じように考えられます。ただ、注意しなくてはならないのが、だからといって必ずしも全て子供のうちに矯正治療を開始しなくてはいけないということもありません。患者さんそれぞれの成長度合い、歯の並ぶスペース、親知らずの生えようとしている向きなど、様々な観点から治療開始時期を考える必要があります。乳歯から永久歯に生え替わるだけで空き歯が治る(歯の隙間が埋まる)ということもあります。
もも矯正歯科では、無理な矯正治療をするのではなく、患者さん個々の状態を正確に判断して、そのうえで「矯正治療をしない」という選択肢を取ることもあります。しっかりと話し合ったうえで、長く安定した歯並びにするお手伝いが出来ればと考えております。

今回は子供のうちに上顎前突を治すメリットをお伝えしたいと思います。
① 指しゃぶりなどの生活習慣から起こる上顎前突
歯は弱い力でも動くということは以前お伝えした通りです。指しゃぶりなどの力が継続的に歯に加わることでも上顎前突になる場合があります。この場合の上顎前突治療は歯並びを治すだけでなく、そういった癖を同時に治していく必要が出てきます。ブラケット(矯正装置)を外した後の保定装置期間において、後戻りを起こさないためにも、もともと上顎前歯が前に出る原因となっていた癖を若いうちに治すことが長期での安定につながります。大人になってからでは癖を治せないということはありませんが、子供のうちの方が習慣を変えやすかったりします。
②骨格性上顎前突
骨格性の上顎前突とは、簡単に言うと上下の顎の大きさの違いによるもの、噛み合わせのズレによるものなどを指します。歯並びだけでなく、顎の骨に関係しているため、子供のうちに治すメリットとしては、顎の成長をある程度コントロールしながら矯正治療を行える点です。
どちらの原因の場合も、子供から治療を開始することで永久歯列で抜歯することなく治療を完了できる可能性が大きくなります。
後戻りのリスクを下げること、骨の成長を考えての歯列矯正を行うことに関しては、実は下顎前突(受け口・しゃくれ)や叢生(デコボコ)においても、同じように考えられます。ただ、注意しなくてはならないのが、だからといって必ずしも全て子供のうちに矯正治療を開始しなくてはいけないということもありません。患者さんそれぞれの成長度合い、歯の並ぶスペース、親知らずの生えようとしている向きなど、様々な観点から治療開始時期を考える必要があります。乳歯から永久歯に生え替わるだけで空き歯が治る(歯の隙間が埋まる)ということもあります。
もも矯正歯科では、無理な矯正治療をするのではなく、患者さん個々の状態を正確に判断して、そのうえで「矯正治療をしない」という選択肢を取ることもあります。しっかりと話し合ったうえで、長く安定した歯並びにするお手伝いが出来ればと考えております。

投稿者 もも矯正歯科 | 記事URL
2015年10月 8日 木曜日
良い歯並びとは?
今日は正しい歯並びとはいったいどういったものかを説明致します。
これまで健康のすべてにつながる矯正治療の価値をお伝えしてまいりました。
また、患者さんによっては、見た目(審美)の改善は第一印象にも影響を与え、そこから自信につながり明るく日々過ごせるようになったという喜びの声も後を絶ちません。
受け口(下顎前突)や出っ歯(上顎前突)などといったすぐにわかる不正咬合(それぞれに種類がいくつかある為一概には言えませんが)だけでなく、矯正専門医が何をもとに診断しているのかをお伝えできれば、少しでも皆さんの歯並びの参考になるかと思います。
1) 全体のバランス:正面だけでなく、ななめ、横からの顔や口元のバランスをチェックします。お鼻の先とあごの先を結んだ線をEラインと呼び、唇の先がEラインに一致しているのが理想です。
2) 左右のバランス:歯並びは一見並んでいるように見えでも、上あごと下あごが水平方向にずれていないかチェックします。
3) 噛み合わせの深さ:オープンバイト(前歯が噛みあっていないで開いている)、オーバーバイト(上顎前歯が下顎前歯に被さり過ぎている)を見ます。上の歯が下の歯に3mm程度被っているのが理想です。
4) 前後関係:横から見た際に上あごと下あごの前後位置関係を確認します。外から見ただけでなく、奥歯を軸に噛み合わせの位置をチェックします。噛んだ時に上の犬歯が下の歯の犬歯とその後ろの小臼歯のちょうど間に入るのが理想です。
5) 歯の状態:虫歯、歯周病を含めて歯の状態、大きさ、色なども確認します。
6) 歯根の状態:歯茎に埋まっている部分の歯根の健康状態を確認します。
7)顎関節:あごの関節の正しい位置でかみ合わせが出来ているか、確認します。これがずれていると、顎関節症が起こる場合もあります。
これ以外にも確認するところはありますし、それぞれのチェックはより細かい診断をしていくことになりますが、ご自身でも確認できるものも含まれているかと思います。また、正面からわかりやすい点だけでなく、様々な角度から確認することで、歯並びや噛み合わせの不都合を発見することも出来ます。また子供の矯正治療の場合、現在の状態から顎の成長の予測を含めての矯正治療計画を立てていくことにもなります。
ひとえに歯並びといっても、実はこのようにチェックする項目はいくつもあります。また、それぞれの状態になった原因も様々です。矯正専門医としてはそれらを総合して診断し、治療計画を立てていきます。ぜひ一度ご自身の歯並びの状態を確認してみてください。その際に今回書いたことが一つの参考になればと思います。

これまで健康のすべてにつながる矯正治療の価値をお伝えしてまいりました。
また、患者さんによっては、見た目(審美)の改善は第一印象にも影響を与え、そこから自信につながり明るく日々過ごせるようになったという喜びの声も後を絶ちません。
受け口(下顎前突)や出っ歯(上顎前突)などといったすぐにわかる不正咬合(それぞれに種類がいくつかある為一概には言えませんが)だけでなく、矯正専門医が何をもとに診断しているのかをお伝えできれば、少しでも皆さんの歯並びの参考になるかと思います。
1) 全体のバランス:正面だけでなく、ななめ、横からの顔や口元のバランスをチェックします。お鼻の先とあごの先を結んだ線をEラインと呼び、唇の先がEラインに一致しているのが理想です。
2) 左右のバランス:歯並びは一見並んでいるように見えでも、上あごと下あごが水平方向にずれていないかチェックします。
3) 噛み合わせの深さ:オープンバイト(前歯が噛みあっていないで開いている)、オーバーバイト(上顎前歯が下顎前歯に被さり過ぎている)を見ます。上の歯が下の歯に3mm程度被っているのが理想です。
4) 前後関係:横から見た際に上あごと下あごの前後位置関係を確認します。外から見ただけでなく、奥歯を軸に噛み合わせの位置をチェックします。噛んだ時に上の犬歯が下の歯の犬歯とその後ろの小臼歯のちょうど間に入るのが理想です。
5) 歯の状態:虫歯、歯周病を含めて歯の状態、大きさ、色なども確認します。
6) 歯根の状態:歯茎に埋まっている部分の歯根の健康状態を確認します。
7)顎関節:あごの関節の正しい位置でかみ合わせが出来ているか、確認します。これがずれていると、顎関節症が起こる場合もあります。
これ以外にも確認するところはありますし、それぞれのチェックはより細かい診断をしていくことになりますが、ご自身でも確認できるものも含まれているかと思います。また、正面からわかりやすい点だけでなく、様々な角度から確認することで、歯並びや噛み合わせの不都合を発見することも出来ます。また子供の矯正治療の場合、現在の状態から顎の成長の予測を含めての矯正治療計画を立てていくことにもなります。
ひとえに歯並びといっても、実はこのようにチェックする項目はいくつもあります。また、それぞれの状態になった原因も様々です。矯正専門医としてはそれらを総合して診断し、治療計画を立てていきます。ぜひ一度ご自身の歯並びの状態を確認してみてください。その際に今回書いたことが一つの参考になればと思います。

投稿者 もも矯正歯科 | 記事URL